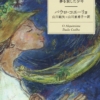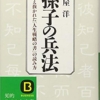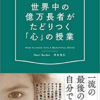【予定説】努力すれば報われるなんて神様は言っていない【資本主義】

【予定説】努力すれば報われるなんて神様は言っていない【資本主義】
こんにちは
yoshi(@yoshiblogsite)です。
みなさんは「予定説」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
ジャン・カルヴァンが唱えた、主にプロテスタント系キリスト教で支持される思想です。
カトリックに代表されるような他のキリスト教の教派や、仏教など他の宗教体系ではともすれば異端扱いされる禁じられた思想ですね。
しかしこれこそが真逆に思える資本主義を推進したと考えられています。
今回はそんな予定説について考えていこうと思います。
すべては神様の手ですでに書き記されているストーリー
予定説において、努力すれば報われることはありません。
神様によってすべては書き記されているのです。
今風に言うと神の手によって仮想現実世界であるこの世界はプログラミングされていて、すべてはシナリオ通りという感じですね。
その中で努力しようが怠けようが、神の手によって全て記載されているので報われる人は報われるし、報われない人は報われません。
新約聖書の「ローマの信徒への手紙」第8章30節に代表されるように、聖書には
「神は予め定められた〜」
という文言がたくさん出てきます。
それが真実なら、人はやる気をなくし努力しなくなりそうですよね。
でもそこが面白いところで、人は努力します。
マックス・ヴェーバーの理論
今の社会はかなり資本主義です。
この資本主義を推進したのが、超禁欲的なプロテスタント的思想であり予定説です。
お金お金、強欲強欲というイメージの強い資本主義ですが、真実は真逆のようで予定説こそが資本主義を推進したとマックス・ヴェーバーさんがすでに考察しています。
超ざっくり説明します。
この矛盾するような解釈を理解するためのキーは、
神は結果に至るプロセスすべてを知っていて、それは書き記されている。
という想定です。
当然神のみぞ知るなのでそれを人間が知ることはありません。
そして、もう一つ
救済されるべき人間は天命に務めて励む人間のはずだ。
という想定です。
この2つが合わさることで、非常に強い力で人は努力するという考えです。
この思い込みの力が強いほど、強い効果が期待できます。
認知的不協和の解消による資本主義の推進
予定説によって努力するプロセスには認知的不協和の解消のメカニズムが隠れていると思います。
前述した想定が心の底に根付いていて、それを現実の自分の生き方に照らし合わせたとき、天命に沿っていなかったとします。
そうすると、そのズレから認知的不協和が発生し、ストレスを感じることになります。
ストレスを解消するためには、自分の生き方を変えるか神の教えを変えるかの2つに1つしかありません。
当然信者にとって、神の教えを変えることはできません。
なので、自分の生き方を変え、天命に沿って努力して生きれば生きるほど
「わたしは天命に沿っている生き方ができているから、最後のときに救済される運命にある」
という安心感を持って人生を過ごすことが可能となるわけですね。
予定説を信じているほどに「絶対に」救済されると確信できるので、その安心感は強まる感じです。
認知的不協和については非常に面白く、また別記事に書こうと思いますが、これによって人は(僕も含めて)洗脳されたり洗脳したりを繰り返しているのがこの世界です。
失敗する恋愛なんかも認知的不協和の産物ですね。
認知的不協和は上手く使えば幸せに通じますし、悪用すればかなり危険な諸刃の剣です。
会社の人事評価システム
ところでみなさんの会社の人事評価システムはどうでしょうか。
納得できる人事評価システムでしょうか。
努力すれば努力した分がしっかり報酬に乗るような制度でしょうか。
大抵の場合そうではないでしょう。
「神のみぞ知る」ならぬ「上のみぞ知る」って感じじゃないでしょうか。
昇進も昇給も、実は「次に誰が上がるか」っていうのは案外決まっていたりしますよね。
よく言われる「上が詰まっているから」ってやつです。
会社は仕組み上、予定説で成り立っているのではないかという場面は多いですよね。
日本においては予定説とは真逆の因果応報の思想
日本においてはプロテスタント的な考えではなくむしろカトリックや仏教的な「因果応報」の思想です。
因果応報の思想は、努力すれば報われるという考え方ですよね。
予定説のような報われるべき人は努力している人だ、ではありません。
しかし会社の人事評価システムについては因果応報よりむしろプロテスタンティズムな感じがしませんか。
これをもって「努力したのに給料上がらない!なんで!」となりますよね。
でもどこかで不満を持ちながらも「不確定な結果」に楽しみを見出すのが人間です。
ギャンブルとかコンプガチャにハマるのと同じ思考回路です。
資本主義社会のシステムは、不確定な結果にギャンブル的な楽しみを見出しながら、認知的不協和の解消に務めて業務を頑張っているイメージがあります。
学習心理学で結論付けられている科学的証拠
学習心理学の世界では、すでに「予告された報酬に対して人間は努力しなくなる」ことがわかっています。
心理学者デシさんのアンダーマイニング現象というやつですね。
かんたんにいうと「自分が好きでやってたのに、報酬をもらうことで報酬をもらえなければやらなくなっちゃう」という現象です。
趣味が仕事になってハッピーだったのにお金もらい始めて仕事になったら楽しくなくなったとか、そういうのも当てはまると思います。
そんな感じで予定説的に会社の人事評価システムは動いていますが、それを予め言ってしまうと努力しなくなるから言わないんですね。
上で説明したような予定説的な認知的不協和の解消を狙っているのでしょうか。
人事評価システムはどこの会社でも、いくら不満が上がろうがなんだかんだ予定説のままです。
実はこれが一番うまく社員のやる気を引き出し、会社としての利益をあげられる方法だったらなんだか切ない気持ちになりますよね。
アンダーマイニング現象もまた認知的不協和と同じく非常に面白い人間特性なので、別記事に書きたいところです。
まとめ:【予定説】努力すれば報われるなんて神様は言っていない【資本主義】
いかがでしたでしょうか。
「時間には過去も未来も今もなく同時に存在するといわれる概念」でも書いた説ですが、おそらくこの世界が仮想現実であるという説は、もともとこの予定説からきているのでしょう。
「【レビュー】アルケミスト 夢を旅した少年【星の王子様に並ぶ必読の名著】」で紹介した本でもなんども「書かれている」という言葉が出てきますよね。
キーは「自分の心の声に耳を傾ける」そして「自分の天命の仕事をする」ということだと思います。
それは自分らしく生きるのが最善ということに繋がるので、自分らしく生きましょう。
宗教が信徒をその教義に従わせることによって幸福を最大化することを目的としたシステムだと考えると、突き詰めた先には人間の性質をついたメカニズムがたくさん眠っているのかもしれません。
教義に盲目的に従っていても、人間心理のメカニズムはよくわからないけど幸福な人生を送れる的な。
個人的にはそのメカニズムを含めてわかって納得してから信じたいところですけどね。
よくよく考えるとそれをわかった上でシステムを構築するのって難易度高すぎて、数千年続く宗教や社会システムを構築した人って本当に別格で天才なのではと思ってきます。
このブログでは毎日更新で「過去の自分が知りたかったこと」をジャンル問わず書いているので、もしあなたの役にも立ちそうなことを書いていたらまた読みに来てください。