分厚い本も速読できる6つの手順の読書法とは【参考書・専門書も積読しない】
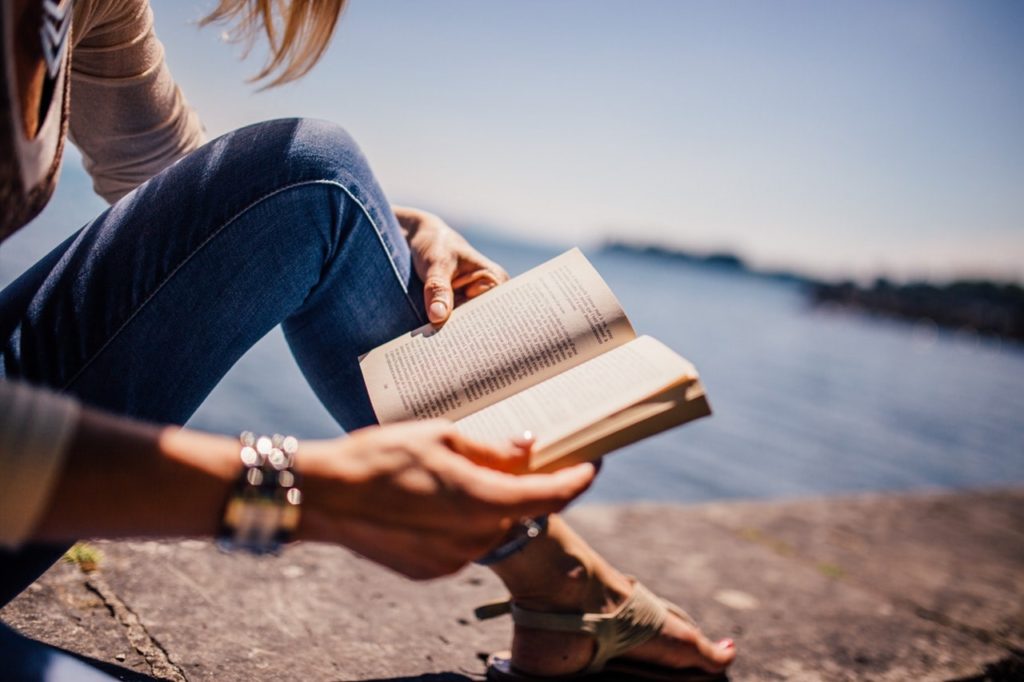
分厚い本も速読できる6つの手順の読書法とは【参考書・専門書も積読しない】
こんにちは
yoshi(@yoshiblogsite)です。
今回の記事は
「本を買ったはいいもののどんどん積読されていく。。。」
「試験やテストが近いから参考書を速く読みたい!」
「うさんくさい速読じゃなくて、ちゃんと頭に残る読書法が知りたい!」
という悩みについて、再現性のある読書術についてご紹介します。
僕自身は慶應義塾大学および大学院を出てITエンジニアをやっていますが、振り返ってみるといろいろな勉強法を試した結果行き着いたのがまさにこの方法でした。
おそらく効率のいい勉強法・読書術を模索して行き着く先はみんなこの方法なのかもしれません。
中学生・高校生のときにこの読書法を知っていたらもっと勉強時間も少なくできて、
ゲームしたりギター弾いたりする時間をもっと持てたのに。。。
と後悔してるので、特に若い人には知っておいて欲しい知識をご紹介します。
結論:もくじの使い方が9割
いきなり結論を言ってしまうと、もくじの使い方が9割です。
のこり1割は心構えです。
手順は下記の通り
- 完璧思考を捨てる
- もくじを眺める
- 読みたい項目を3つくらい選ぶ
- 項目の中身を推測する
- 最初の1行と最後の1行だけ読む
- 読み進めるか別の本にするか判断する
では、順に説明します。
ちなみに小説やのんびりダラダラ中身を眺めたい本を読むときはこの方法は使いません。
なぜなら目的が知識のインプットではなくその時間を過ごすことだからです。
あくまで勉強のための方法だと思ってください。
【速読法の手順1】完璧思考を捨てる
まずは学校で1ページ目から順に本を読んでいって、1ページずつ中身を完璧に理解していこうとする完璧思考は排除しましょう。
おそらく完璧に読まなくちゃという強迫観念は、この間違った学校教育にあると思います。
というか別に学校もそのつもりはなくて、単純に授業を進めていくとどうしてもその形で進めざるを得ないだけかもしれませんが。
完璧思考を持ち続けると、小説などの場合はいいんですが教科書や参考書、専門書のような分厚い本や小難しい本を読むときは途中で萎えます。
読まなければまったくもって意味はなく、まさにお金のムダです。
それよりはるかに意味がある読書法をするために完璧思考は邪魔者以外の何モノでもありません。
まず完璧思考を捨てましょう。
【速読法の手順2】もくじを眺める
完璧思考を捨てることができたらもくじを眺めます。
ここが非常に重要で、もくじを読みながらあれこれ考える時間を慣れない内は10〜30分以上もってもいいくらいです。
大半の人がもくじを甘く見ていますが、速読できない原因の9割はここにあると思います。
もくじはじっくり眺めて、頭の中にその本の地図を描きましょう。
【速読法の手順3】読みたい項目を3つくらい選ぶ
もくじを眺めたら、読みたい項目を3つくらい選びましょう。
めんどくさい人は1つでもいいです。
もしほかの項目は全部読めないとしたらどれを選ぶかと考えると選びやすいと思います。
この手順の目的は、自分の興味を明確にすることです。
実験によると、しおりにこの項目をメモしておいてことあるごとに意識付けすると本を読み終わるまでモチベーションを維持できるそうです。
【速読法の手順4】項目の中身を推測する
読みたい項目を選んだら、項目の中身を推測しましょう。
どんなことが書いてあるのか、予測することが大事です。
ここで多少頭を使って推測することで速読してもきちんと記憶に残るようになります。
【速読法の手順5】最初の1行と最後の1行を読む
推測が終わったらいよいよ項目を読んでいきます。
とはいっても最初の1行と最後の1行だけでいいです。
予測したないようを少し具体的にしていきましょう。
もくじを眺めて作った頭の中の地図ももう少しハッキリしてきたと思います。
ちなみに読む時間があるなら1行よりもっと読んでもOKです。
気の向くままに読みましょう。
【速読法の手順6】読み進めるか別の本にするか判断する
先ほど選んだ3つくらいの読みたい項目について最初の1行と最後の1行を読んだら、とりあえず自分がこの本で興味をもった内容について少しは知っている状態になります。
基本的にはこれで「本を読み終えた感」に浸りましょう。
頭の中の地図はまだまだモヤがかかっていると思いますが、自分の知りたいところは見えてきていると思います。
自分が予測した内容とズレていたでしょうか?
まだズレてるかどうかわからないでしょうか?
いずれにせよもっと答え合わせをしたいと思うでしょうか?
知識のあな、頭の中の地図を埋めていきたいと思うでしょうか?
もしそう思わないなら、その本はそれ以上読み進める価値はありません。
売るなりなんなりしてさっさと別の本を読むようにしましょう。
逆に埋めたいとか、どうしてもその本を理解しないとダメだという場合は、最初に選んだ3項目を中心に読み進めていきましょう。
そのときに気になったところはメモして自分なりにまとめておく&1ページ読んだら目を閉じて中身を思い出すようにすると記憶に残りやすくなるのでおすすめです。
3項目を読み終わったら、他の項目も同様な感じで興味を持ったところを順につまみ食いして頭の中の地図を埋めていきましょう。
興味の向くままにつまみ食いしてすべての地図が埋まりきったら、いつのまにか本は読み終えているものですし、知識も案外定着しています。
まとめ:分厚い本も速読できる6つの手順の読書法とは【参考書・専門書も積読しない】
いかがでしたでしょうか。
読書はためになりますが、できることなら高速に知識をインプットしたいですよね。
今回ご紹介した方法は一生勉強する上で必ず役に立つと思います。
勉強だけでなく、僕は仕事で大量の資料をさばく必要があるのですが、それも高速に内容を理解してさばくことができるので、上手く活用すればいつどこにいてもベースアップできるでしょう。
ちなみに今回の記事をまとめるにあたりDaigoさんの動画をかなり参考にさせてもらっているので、動画で知りたい方はぜひどうぞ。
学生時代に荒削りだったこの方法をこの動画のおかげでキレイに整えることができました。
このブログでは毎日更新で「過去の自分が知りたかったこと」をジャンル問わず書いているので、もしあなたの役にも立ちそうなことを書いていたらまた読みに来てください。
















